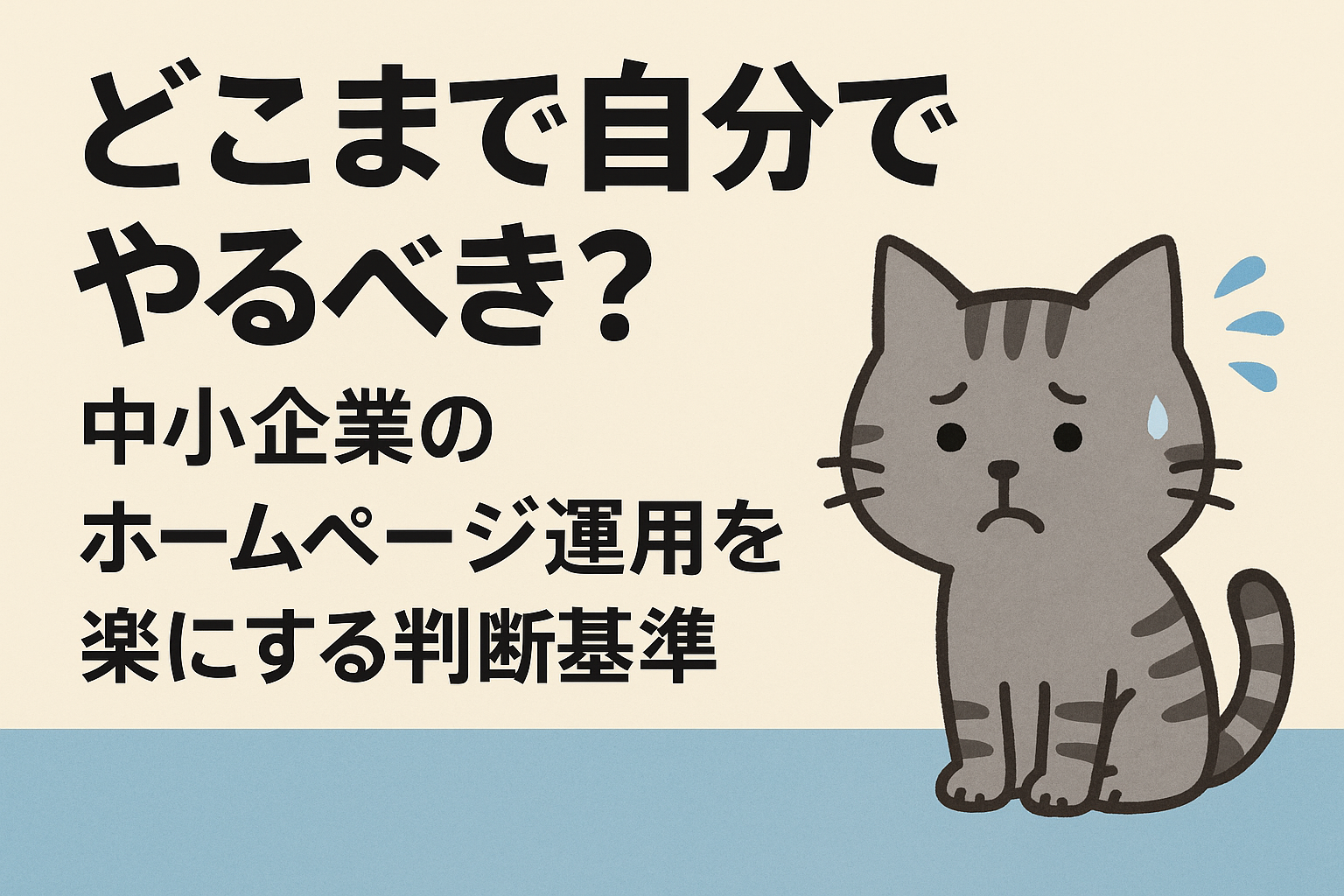ホームページを作ったはいいけれど――
「更新や問い合わせ対応まで全部やっていて大変…」
「SEOやデザインのことまで手が回らない…」
そんな声をよく聞きます。
特に中小・零細企業では、担当者が他の業務と兼任しているケースが多く、
「どこまで自分でやるべきか」「何を外注すべきか」の線引きがあいまいになりがちです。
この記事では、ホームページ運用の“分担”を明確にする基準を紹介し、
「頑張りすぎない運用」で成果を出す方法を解説します。
■ なぜ“全部自分でやる”と続かないのか
ホームページの運用には、
- 情報発信(記事更新・ニュース掲載)
- 問い合わせ対応
- SEO・アクセス分析
- デザイン修正
- サーバー・セキュリティ管理
など、実は多岐にわたる業務が含まれています。
一人で全部やろうとすると、次のような問題が起きがちです:
- 更新頻度が落ち、サイトが放置状態に
- 分析や改善まで手が回らず、効果が見えにくい
- 専門外の作業に時間を取られ、本業が疎かになる
つまり、「何でも自分でやる」ことが成果の足かせになることも。
大事なのは、“戦略的に手放す”勇気です。
■ 自社でやるべきこと(=情報と想いの発信)
企業のホームページで、自社だからこそ伝えられる部分があります。
それが「一次情報」や「顧客との接点」に関する内容です。
▶ 自社でやるべき主な業務
| 項目 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| お知らせ更新 | 新商品・休業日・イベント情報など | スピード重視・現場発信が強み |
| ブログ/コラム | 社長メッセージ、事例紹介など | 自社の想いや強みを伝える |
| 問い合わせ対応 | メール・フォーム返信など | 顧客対応は自社の責任範囲 |
| SNS投稿 | 日常の活動や雰囲気発信 | ファンとの距離を近づける |
📍 ポイント:
「自社でしか書けない内容」=会社の“人柄”を伝える最大の武器です。
文章が完璧でなくても構いません。更新して“動いている印象”を保つことが大切です。
■ 外部に任せるべきこと(=専門知識・技術が必要な部分)
一方で、専門性が高く時間がかかる作業は、思い切って外注するのが得策です。
▶ 外注を検討すべき主な業務
| 項目 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| SEO分析・キーワード設計 | 検索順位や流入データの解析 | 専門ツール・経験が必要 |
| デザイン修正・バナー制作 | ページの見た目やレイアウト変更 | センスと設計知識が必要 |
| サーバー管理・バックアップ | 障害対応・SSL更新など | リスク管理・緊急対応が難しい |
| ページ速度改善・プラグイン管理 | WordPress等のメンテナンス | 技術的作業で時間がかかる |
📍 ポイント:
自分では“できる”けど“得意ではない”部分こそ、
外部のプロに任せるとコストパフォーマンスが上がります。
■ 判断基準は「時間×効果×リスク」
外注するかどうかを判断するときは、
次の3つの軸で考えると分かりやすいです。
| 判断軸 | 内容 | 自社でやる | 外部に任せる |
|---|---|---|---|
| 時間 | 自社でできるか・手が回るか | ◎ 手軽・短時間 | ✖ 長時間かかる |
| 効果 | 自社が成果を出せるか | ○ 伝える・反応が見える | ◎ 分析やデザインの最適化 |
| リスク | トラブル時に対応できるか | △ 内容更新は対応可 | ◎ セキュリティ・技術対応に強い |
📍 目安:
- 「1時間以内で終わる」なら自社で
- 「1日以上かかる」なら外部に任せる
この線引きを持つだけで、運用負担が大幅に減ります。
■ 自社×外部の“ハイブリッド運用”が理想
実際は、「全部自分で」か「全部外注」かの二択ではありません。
最も効率的なのは、自社と外部のハイブリッド運用です。
たとえば:
- 自社:お知らせ更新・SNS投稿
- 外部:定期的なサイト分析・改善提案
- 年1回:全体デザインの見直し
このように役割を分ければ、
担当者の負担を減らしつつ、常に最適な状態を維持できます。
■ まとめ:頑張りすぎず、“仕組みで回る”ホームページ運用へ
ホームページ運用の目的は「更新作業」ではなく、「成果を生むこと」。
そのためには、人ではなく仕組みで回る体制づくりが欠かせません。
✅ 自社でやる:現場のリアル・お客様対応
✅ 外部に任せる:技術と分析
この線引きを持つことで、
ホームページ運用はもっとラクに、もっと成果につながるものになります。
✉️ 最後に
「更新が負担」「運用の優先順位が分からない」と感じたら、
まずは“やらないことを決める”ところから始めてみましょう。
外部と上手に連携すれば、
ホームページは“働く社員の一人”のように成果を出してくれます。
WEB担当者に役立つ情報を毎日更新中!